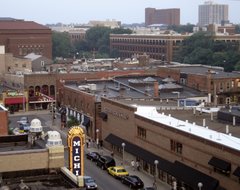自分らしく生きたかったらエゴイストになりなさい ヨーゼフ・キルシュナー
平和の唱道者たちはこれまで以上に戦争で大もうけするでしょう。ぐうたらのなまけ者どもは、これからも有能な
者たちの汗と努力の結晶を食いものにしてしてのらくらと暮らしつづけるでしょう。有能な者たちはなんのためとも
知らず、ただ死にものぐるいで働くだけのことでしょう。健康産業はますます活状を呈し、ブームはさらに続くでしょう。
それでも、人類の病気がますますふえていくことに、誰も疑問を投げかけたりはしないでしょう。
***
その期待はものの見事に裏切られるでしょう。なぜなら二十一世紀もこれまで同様に三階級社会という人類最古の
システムが引き続き私たちを支配することになるからです。これは絶対に疑いありません。ここでいう階級とは次の三つをさします。
*愚かな人たち
*ずるがしこい人たち
*真にかしこい人たち
どうしたらいいかわからない愚かな人たちは、自分が何を信じ、何を考え、何を望み、何を買えばいいかを教えてくれる人たちを、
これからも探し求めるでしょう。そして、ずるがしこい人たちは、親切に笑って愚かな人たちにあれこれ助言を与えてたっぷりもうけて、
甘い汁を吸うことでしょう。
***
(エゴイストの十戒)
1.権利より先に義務がある。
2.お金がなければつかわない。
3.仕事ができるなら勤め口はかならずある。自分の値打ちは自分で決める。
4.自分と調和できるのなら、世界とも調和できる。
5.人を責めるのは自分自身を責めるのとおなじこと。それは自分への怒りを相手にぶちまけているだけのこと。
6.何がやりたいかわかっているなら、誰も口出しなどできない。
7.誰にでもなまける権利がある。しかし自分の有能さを犠牲にしてまでなまけることはない。
8.有能というのは自分自身にとってであって、他人にとってではない。
9.あることについて語れば語るほど、それがわからなくなる。
10.多くを知れば知るほど、ますますそれについて語る必要はなくなる。内容のないことを百回言うよりは、黙っているほうが時として効果的。
***
かしこい人たちは自己を解放することによって自由を獲得しようとするのですが、それは自分の人生に対して、
はっきりとしたイメージをもつことによってのみ得られます。
***
「誰も他人に幸福を与えることはできないし、他人から幸福を奪うこともできない。自分の責任は自分にしか負えない」
***
「人生の舵は自分でとる、最後の決定は自分で下す」
***
「どうやらこれが、賢者の階級に所属するための鍵のようです。自分が不幸なのは他人のせいだと逃げ口上ばかりならべるのは、
おろかな人だけがすることです。
指図したり取り締まったりするのがずるがしこい人たちの習性だとすれば、どうしてよいかわからずに服従するのが愚かな人たちの
習性といえそうです。だから、両者はたがいに依存しあっています。
***
イメージしたら信じることです。信じればこれまで疑っていたことも実行する力がわきます。信じるということは、
想像はできるというレベルから一歩踏み出して、想像もできないことを実現することなのです。ただし正当な方法をとること。
***
しっくりくる人生を送るには、何がほんとうに必要なのかを知ることです。必要なものを手に入れるには、何をあきらめなくては
ならないかを知ることです。
***
教育というのはどんな教育であれ人を不安がらせ、おどし、こわがらせるのが常套手段です。人は不安になると言いなりに
なってしまうものだからです。しかし、あなたは自分で自分を教育するのですから、他人の言いなりにはなりません。
***
あなたの言うことが正しい必要はありません。人がそれをほんとうだと信じてさえいればいいのです。権威というのは、
あなたが正しいことを言っているからではなく、あなたが正しいことを言っていると人々が信じているから成立するのです。
あなたが権威をを利用するときは、もしそれが見抜かれたときには逆にあなたに不利なかたちで利用されることもお忘れなく。
***
もっとも強い説得力をもつのは権威などではなく、あなたが日々の行動のなかで着々と積み重ねている自分への確信に
ほかなりません。
***
けなしたりほめたりするのは、相手をゆさぶるための手段です。人からほめられないとやっていけない人、人からけなされるのを
恐れる人、こうした人たちは他人に左右されています。
何がしたいのかはっきりさせましょう。自分を信じて自分のものさしで行動してください。そうすれば誰も、ほめたりけなしたりして、
あなたを不利な状況へ追いやることなどできません。
あなたをほめる人は、あなたを味方につけたがっているのです。あなたをけなす人は、あなたをおとしめることで自分が上に
行きたいのです。あるいはあなたの失敗にあげつらうことで自分の失敗の言い訳をしようという魂胆でしょう。ほめたりけなしたり
というのは、相手をゆさぶるための戦術です。この戦術をつかって、ずるがしこい人たちは愚かな人たちを統率しているのです。
他人をけなす人は、それによって自分の権威を打ち立てようとしているのです。あなたは自分自身の確信で人を説得するので
あって、自分の権威を前面に打ち出す必要はありません。権威にだまされるのは自分に権威のない証拠です。
それが利益をもたらすなら、あなたもほめたりけなしたりの戦術を駆使して相手をゆさぶってみてください。他人が不利益を
こうむるのは知ったことではありませんが、あなたが利益を得るのは大事なことです。
誰でも自分に対して責任をもたねばなりません。だから他人にたくみにあやつられて油揚げをさらわれたからといって、
なんの弁解もできません。
***
どんな協力関係にせよ、はじまりはあなた自身です。あなたが自分を信じて、自分自身と調和がとれていれば、
あなたは自分自身のもっとも信頼のおけるパートナーです。
自分自身と調和が取れているとは次のようなことをいいます。
*敗北を喫しても自分を責めたり言い逃れを考えたりせずに、敗北から学ぼうとする。
*自分自身を信じていて、誰もその自信をゆるがすことができない。
*自分に対して責任を負っていて、誰もその責任を肩代わりしようなどとちょっかいを出さない。
*自分を信じて、決して自分を否定しない。ただし、誰かをたくみにあやつってひともうけするために自分をいつわるというのなら話は別。
パートナーシップを結ぶ意味は、一人で問題を解決するよりは二人でいっしょに取り組んだほうがうまくいくということにあります。
パートナーシップでいちばん大事なのは、平等ということではなく、相互補完ということです。
パートナーシップとは、パートナーに対する思いやりではなく、創造的なぶつかりあいのなかで相互理解を深めることをいいます。
パートナーシップとは、相手を尊重すると同時に自分も尊重されることです。
パートナーシップとは、それぞれが投資したよりもたくさん返ってくるということを意味します。
パートナーシップにおいては、それぞれが自分なりに正しいのです。つまりあなたはパートナーの真理を尊重するけれども、むこうもあなたの
真理を尊重するのです。たとえパートナーがあなたの真理を尊重しなかったとしても、それがあなたの真理であることには変わりはないのです。
おなじく、あなたがパートナーの真理を尊重しなくても、それはやはり相手の真理であることに変わりはないのです。
パートナーシップがあなたによろこびよりも苦痛を与えるようになったら、それは意味を失います。そのときは相手にかまうことなく決定を下すことです。
あなたが自分自身と幸せな関係でないのなら、どんなパートナーとも幸福にはなれません。自分を愛していないのに、人を愛せるはずがありませんから。
あなたが他の誰よりもあなた自身を信じているのなら、どんなパートナーにも幻滅することはないでしょう。
パートナーシップの原理は、階級組織の原理と真っ向から対立するものです。パートナーシップにおいては、
何よりもまず個人個人が自分に対して責任を負い、連帯責任はあとになります。
***
社会に庇護を求めるものは、自分で自分を守ることができない人間です。こういう人は庇護者たちからいいようにあやつられて貢がされてしまうでしょう。
モラルというのは、自分のものさしをもたない愚かな人たちをあやつるためのよい口実になります。
モラルをもてあそんで金もうけをしているずるがしこい人たちは、モラルの基準をひじょうに高く設けていて、愚かな信奉者たちがいくら努力しても、
その基準を満たすことはとうていできないのです。そのために信奉者たちはつねにダメ人間のレッテルをはられ、彼らの人生はたくみにあやつられてしまうのです。
しかし何より自分を信じ、自分のものさしだけで生きている人は、罪悪感などで人のいいなりになったりはしないのです。
***
あなたは次のような三階級社会のなかで生きています。
*ずるがしこい人たちの階級―彼らは愚かな人たちに何を考え、何を信じ、何を望み、何を買ったらよいかをあれこれ指図してぼろもうけしている。
*愚かな人たちの階級―彼らは自分が何を考え、何を信じ、何を望み、何を買ったらいいのか自分で判断できないので、ずるがしこい人たちのいいなりになってしまう。
*真にかしこい人たちの階級―彼らは自分が何を考え、何を望み、何を買うべきかをよく心得ていて、自分のものさしにしたがって行動する。
***
自由な社会というのは自分自身が自由である人にとってのみ存在するものです。自由であるためには、できることはすべて
やってみることです。そうすれば、あなたはいつでもどんな社会でも自由でいられます。
***
文化というのは、あなた自身の心のなかにあります。だから、あなたの生き方そのものが文化のあらわれなのです。
文化というのは生命のあるがままの姿であり、誰かに指図されたり管理されたりするものではないのです。
***
マスメディアというのは正義やモラルをかかげるのが大好きですが、彼らは決して倫理的な集団ではありません。
彼らはスポンサーの利害にかなうように言論を操作する企業なのです。
マスメディアは人工的な世界をつくりあげ、視聴者や読者はそれを見たり聞いたり読んだりして、現実では満たされない
欲求のはけ口を見つけるのです。つまりマスメディアは自分の人生でナマで生きることのできない人たちのために、
作りものの人生を提供しているのです。
毎日現実とむきあって、あなた自身のナマの人生を生きてください。あなたはあなたにしかない人生を体ごと生きているのであり、
傍観しているのではないのです。
マスメディアなんていうものは、あなたの役に立つように、あなたのものさしにあわせて利用すればいいのです。
あなたの人生を毎日の現実のなかで精いっぱい生きてください。そして現実に背を向けて映像の世界に逃げ込んだりしないで、
自分の手で問題を解決してください。
自分の夢を見ましょう。自分の苦しみを苦しみ抜きましょう。そして自分の力で、自分にあった世界をつくりましょう。
自分の手で人生をつむぎだす人は、メディアのヒーローに自分の幸福を重ね合わせる必要などないのです。
***
宗教や政党は信者や支持者たちに全員が幸福になることを約束しますが、そのかわりに個人の自由は失われます。
***
自分を変えれば自分が住む世界も変わります。これは個人主義の考え方で、誰もが自分自身の世界を築くことができるというものです。
ただし、その責任は自分が引き受けなければなりません。
自由競争社会では、誰もが他人を犠牲にして自分の利益をものにするチャンスにめぐまれています。
だから自由競争社会というのは計算ずくめのゲームのための格好の舞台なのです。
自由競争では思いやりという視点はありえません。自然界における弱肉強食の原理とおなじく、誰もがわが身かわいさだけで生きているのですから。
ずるがしこい人たちは、なにかにつけ平和・平等・隣人愛などといった希望を説いて、愚かな人たちを自分たちの利害にしばりつけます。
残された唯一の自由は、ずるがしこい人たち、愚かな人たち、そしてかしこい人たちのいずれの階級に所属するかを自分で決定するということだけです。
いかなる選択をするにせよ、一市民として知っておかねばならないのは、自分の人生を意味あるものにするには、何かをあきらめなければならないということです。
あなたが自由でいられるのは、他人と比較しないときだけです。なぜなら、そのときのあなたは自分が何をしたいのか、ほんとうにわかっているからです。
***
潜在意識に埋め込まれた障害は、あなたが意識的な意志決定をしても取り除くことはできません。それを取り除くには、あなたの潜在意識にあなた自身の
プログラムを植えこむしかありません。そのプログラムとは、あなたが自分で自分を教育するということなのです。
潜在意識に到達するには、欲しいと思うものをねばり強く思い続けることです。どのくらいねばり強く思いつづけるのかというと、あなたの行動をさまたげている
すべての潜在意識よりもさらに深く根強くあなたの思いが植えこまれるまでです。
そこまで思いつづけると、あなたは思いどおりの自分になることができます。そしてこうしたことが、ごく自然に堂々と行なえるようになります。
このように潜在意識の世界にあなたのプログラムを植えこむのは、あなたがリラックスしているときにかぎります。リラックスするには、静かな場所で
楽な姿勢をとり、静かに深呼吸して、あなた自身に精神を集中することです。
リラックスした姿勢、深呼吸、そして自分自身へ意識を集中することによって、あなたは他人が押しつけた生活のリズムを脱却して、
自分に合ったリズムに乗り換えることができるのです。
***
忘れてならないことは、どんな行動もトレーニングを積み重ねた上でなければ実現しないということです。あなたがなにかを
なしとげようとするならば、それが自分のイメージどおりに自然にできるようになるまで、一歩一歩ねばり強く実践を通じて
改善していかなければならないのです。
つまり、それはどういうことかというと「計画と決断の段階では頭をつかってよく考えよ、しかし、行動するときには疑う気持ちなど
かけらももたずに、ただ成功の確信だけをもって行動せよ」ということなのです。
***
問題を解決するには、その問題を把握しなければなりません。問題を把握するには三つの段階があります。
*その問題がどんな影響を及ぼしているかを知る。
*その問題が他のこととどう絡みあっているかを知る。
*その問題の原因を知る。
問題とのつきあい方には、次の二つがあります。
*問題がどんな影響を及ぼしているかわかっているのに解決しようとせず、それを忘れてしまおうとする。もちろんそれで問題は解決しません。
*問題の因果関係を把握してよりよい状況をつくりだそうとする。
問題の因果がわかっている場合は、次の三つを駆使してください。
*あなたもしくは人の経験。
*あなた自身の直感。
*あなたの創造力と想像力。
ねばり強く調べあげ、きちんと問いただしていけば、問題の因果関係はかならずつかめます。
問題の原因を解明するもっとも重要な問いは「なぜ?」ということです。
***
健全なエゴイズムをぞんぶんに発揮しながら人生の達人になるというのは、まったく個人の問題です。ずるがしこい文化人や
政財界の幹部どもは、何かにつけ芸術がどうの文化がどうのとこせついた定義づけをしたがりますが、人生の達人になるという
ことはこんなやからのおせっかいとはなんの関係もない事柄なのです。なぜなら、人生の達人になるわざというのは人の役に立つ
ような代物ではなく、もっぱら自分を豊かにするために自分で身につけるものだからです。
そもそも文化とか芸術というものは、愚かな人たちの哀れな人生を少しでもくつろげていくらかでも面白いものにしてやろうと考え
出されたものです。そして、そのなかでもっとも秀でているのは、この人生の達人芸とでもいうべきものなのです。人生の達人芸
というのは、ただ食うために生きているのではなく、自分を乗り越えようという志をもった者なら誰でも自分のものにすることができます。
その際に重要なことは、この人生の達人芸というのは自分を豊かにすること以外に何の役にも立たないということです。人生の
達人は、人から尊敬されるためにパフォーマンスをする必要などまったくないのです。自分というものを最高に尊敬していれば、
それで十分なのです。
***
心配するというのは、あなたが自由でない証拠です。あなたが自由人ならば自分のメロディーで自分にあった踊りを踊るで
しょうし、人の評価など必要としないでしょう。
あなたが自由人で自分のメロディーにあわせて踊りを踊る人ならば、あなたは自分の自然の欲求にしたがって生き、自分の
生き方を無理やり型にはめたりはしないでしょう。だから自由人であるためには自由な創造力が必要なのです。
***
人がとうてい思いつかないようなことを考えてください。型にはまった考え方しかできない人たちには、とうてい思いつかないような
解決策を見つけ出してください。人がとうてい不可能だと思っていることをやってください。
自由というのは、人があなたに与えてくれるものではないのです。自由はあなたのなかにしかありません。やってできない
ことはないと、あなたが自分を信じたその瞬間に自由が生まれるのです。
自由人になるわざを身につければ、目標をかんたんに定めることが出来るようになります。しかも、その目標が実現しようが
しまいがどちらでもへいちゃらなのです。なぜなら自由人にとっては、そこへ至る道すじそのものが目標だからです。もちろん
途中で放棄してしまっては、自由人としての面子は丸つぶれかもしれませんが。
***
自由というのは偶然手に入るものではありません。いまここで頭をはたらかせてあなたの自由を磨いてください。
いまここで自由ならば、「明日はどうなるのだろう?」なんて考えたりしないこと。頭のなかが自由ならば、どこにいても自由になれるのです。
あなたの思考をコントロールする能力が増せば増すほど、あなたの自由も大きくなります。あなたの潜在意識に思考や
イメージをプログラムするときは、よく注意を払いましょう。そのときの合言葉はつねに「今日何が起ころうと、私はいつも自由で幸福」
というものです。
あなたの精神に自由が根付いていれば、いくら人から束縛されても、あなたの心のなかは自由です。これが自由人でいる
ための秘訣なのです。
***
人に勝って自分が優秀であることを証明してみせることはありません。あなたが自分で知っていれば十分です。
人生で大切なのは人よりすぐれていることではなく、自分の力でできるかぎりのことをすることです。ゲームに負けたなら
敗北から学べばよいのです。自己不信に陥ったり言い訳したりせずに、敗北から学ぶ。これこそが自分に勝つということです。
***
ずるがしこい人たちは愚か者どうしを戦わせて利益を得ています。これがゲームをたくみにあやつる彼らの戦略です。
かしこい人たちは人のために戦いませんから誰からも征服されることはありません。
戦いに勝ちたいという願望は、人を攻撃することからはじまります。しかし人を攻撃するということは自分を攻撃することに
ほかならないのです。
自分に対する攻撃は問題が解決できないおのれの不甲斐なさに対するいらだちからはじまります。自分の存在証明が
出来ない人は、他人を攻撃することでそれを得ようとするのです。
あなた自身と仲良くすること。自分の問題は自分で解決すること。人をおとしめて自分をもちあげたりしないこと。
これができれば、あなたは戦わずして人生に勝つことができます。
***
あなたは幸福を味わうことによって成熟を重ねますが、同時に不幸な体験によっても成熟は増していきます。
不運に見舞われたことがなければ、ほんとうに幸福になることはできません。不自由を重ねてようやく自由の境地にたどりつく
ことができるのです。だから一つ学んではまた次へという姿勢をなくしてはいけません。
「残された人生は自分の欲求と気持ちのおもむくままに生きて、人からあれこれ指図されるような関係は全部捨ててしまおう」