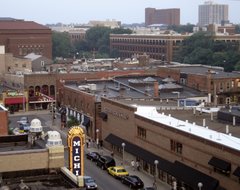人間の見分け方 谷沢永一
・「いつ」「どこで」「どのように」頼りになるかで、頼りになる人は違ってくる。
・頼りになる人を確認するポイントは、組織全体に目配りがあるかどうか。
・一緒にいると気分がいいという人も見落とせないタイプ。
・個人レベルでは話を聞いてくれる人が一番。
・自制心のある人は欲を抑えられる。ただし、ポジションや境遇で抑えている人もいるから注意。
・年を取ると、自制心は弱まる。
・信用は本職をしっかりしていることが絶対条件。お金の払いがきれいであることは必要条件。
・どこへ行っても通用する人間などはいない。
・世の中はすべて偶然の組み合わせ。誰にでも、どこにでも通用する公式はない。
・女は世間の代表。女にもてる男は世間にもてる。女に嫌われるようでは駄目である。
・人を喜ばせる嘘は人間関係で大事である。
・運がよくても将来への展望がない人は頼りにならない。
・「自分と合うものがある」「ピンとくるものがある」「ウマが合う」という感覚があったら、必ず付き合いを持ちたい。
・「この人と付き合いたい」と思う人に出会ったら幸せである。
・好きな人、付き合いやすい人には無理がない。頼りにしようと思って付き合うのは無理がある。
・権勢家との関係を作るのは、出世する前から付き合うのが鉄則。鍋が煮えてからでは遅い。
・凡人は権力に近づかず、小細工しないで生きる方が賢明。
・無能とは能力がないことではない。有能の証を立てる機会がなかったのである。
人情味とは人情味が重要であると知ったときに沸き起こる情合いではないかと思う。
いわゆる思いやりというものができて初めて、人情の価値がわかる。男が本当の人情味を持つのは、四十歳以上だと思う。
・エネルギッシュな上司が大失敗する時に、自分まで巻き込まれないように警戒する。
・成果を横取りされても余り気にしない。それでも悔しかったら別なところで取り返せばいい。
・責任を取らない立場に身を置き、部下の成功を自分の手柄にするのが官僚の処世術。
・人情味が重要とわかる年齢になって、人情味が出る。若い時に人情味がある人はくせ者かもしれない。
そもそも人生からして、自分の計画通りにいくものではないと私は思う。まず人生は常に偶然によって組み立てられる。
そこから出発しないことには仕方ないのではないか。つまり、合理的にはいかないということである。ものの本を読むと、アメリカ社会は
日本よりも理屈あるいは利害で割り切れるらしいが、それでも利害だけでも理屈だけでも決まらないようだ。やはり何かプラスアルファがある。
・スカウトされて成功した人は、上位の人の勧誘や紹介がある。
・誘ってくれる人とウマが合うか、心変わりしない人かをチェック。
・誘ってくれることをおろそかに思ってはならない。
・人生に人間関係も偶然のなせる技である。合理的にはいかない。
・だらしない人とはとばっちりをくわない距離で付き合う。
・全身をピカピカに飾っている人は自己愛の塊。自分本位でいながら自信がない。
・賭け事の好きな人に金を貸してはいけないが、能力を期待できるかもしれない。ただし、扱いにくい。
・ズケズケと直言してくれることに感謝する度量を持つ。
霧島昇は地方巡業で司会を務めた人の名前を最後まで覚えなかったそうだ。霧島昇はただ喉を聞かせることに没頭する機械なのである。
身持ちは正しく、どこからみても立派な人物だが、どこの舞台で何時から歌うということだけを考えているのだから、社会的な活動に対する意識は希薄だ。
要するに、講談に出てくる左甚五郎のように社会性はゼロである。
・嫉妬深い人は正直で善人。でも、付き合いづらい。
・嫉妬がひどい人と思ったら近寄らない。
・こちらに好意があれば大欲の人に見え、好意がないと強欲の人に見える。
・自分のことしか関心のない人は工芸品、役に立つ機械だと割り切って付き合う。
・人間関係で無理をしない時のために挨拶言葉がある。
・人間関係には、中身のある関係と中身のない関係の二種類がある。
・遅刻常習犯は心構えに問題あり。
・憎む相手が多い人は社会性に乏しいかもしれない。
・裏切りは前もってわかるものではない。
・分け隔てのない人は自分を出していない。隠したいことがある要注意人物。
・感謝の気持ちには有効期限がある。いつまでも感謝してくれるなどと思うな。
・無責任は諸悪の根元。なおかつ直る見込みはない。
「ケチと臆病は生まれつきなので直らない」
これは私が間違いないと考える言葉である。
まず、ケチというのは、いまの一瞬だけに生きている。いま何かを出費することが嫌ということだから、未来がない。動物と一緒なのである。
そうすることによって、自分がどう思われるかという未来測定がない。ということは、情というものが冷えている。
・ケチはいまの瞬間だけを生きていて、情が冷えている動物である。
・お金を持てば持つほどケチになる。
・情報力は人間関係学。情報力のない人は人間関係を持たない人である。
・慎重と臆病の差は決断のタイミングの差。
・味方がイライラする直前に決断しないと、敵に負ける前に味方に負ける。
高校教師が君が代、国家掲揚に反対して騒がれたが、教師がなぜ日の丸を憎いのか。
素直に日の丸を見て憎いと思うなどとは、人間感情では考えられない。オリンピックを見たらすぐにわかる。一番高い位置に日の丸があがり、
君が代が流れると、誰もが喜んでいるではないか。では、なぜ君が代と国家掲揚に反対するのか。要するに、高校教師という立場に不平があり、
面白くないから、日の丸、君が代に反対し、逆らうことで満足しようとしているのだろう。
・高慢な人の仮想敵国にならないように注意。
・高慢な人には尊敬するふりをして敬遠するのが得策。
・清貧の人は凡人の欲望をわかってくれないから難儀な相手。
・いつも不機嫌な人を気にしない。不機嫌とは対人関係に無関心であることの表れ。頼りになってくれるはずがない。
・不平不満ばかり言って能力のない人は危ないから付き合わない方がいい
・人間の間で「受け渡しできるもの」と「受け渡しできないもの」とがある。
三成は颯爽としたかったのだろう。あるいは自分を英雄に仕立てたかったのだろう。その一方で、同時に天下取りをやろうとした。
そこで目的が分裂している。だから、天下を取るという外面だけに絞り、なりふり構わなかった家康が勝った。
・人間関係を切る理想的な方法は切り捨てるという姿を取らないこと。
・一つの人間関係を切ることは、腹をくくって今生の縁をきるというぐらいの気持ちがいる。自分をよく思ってもらおうという色気は失敗の元。
・自分に矢が飛んでくることも覚悟する。なまじ凡庸な人間が簡単に人を切ろうと思ってはいけない。
・人を切り捨てる動機は公に利することが最低条件。
・やるならとことんやる。中途半端は駄目。
芸能人はうぬぼれてもよろしい。しかし、それ以外の仕事をする人間が評判の良さを真に受けていい気になるのは駄目である。
なぜなら、自分の能力に対する反省がないからだ。
友達は二十歳の頃から営々と作るものである。若いときから情を発し、その積み重ねの上にやっと生まれるのだ。「何かをしてあげたい」という気持ちが
生まれたら、「やあ」と言って声をかけるような人懐かしい態度がおのずからできるのではないかと思う。能動的に情を発し、気持ちを働かせる人は心の温度が高い。
逆に、「して欲しい」ばかりの人は心の温度が低い。心の温度を高くして、得をするのは自分である。
・よい評判にうぬぼれている人は危なくて頼れない。
・人は言葉の端々に本音が出るものだ。
・悪評のある人に宝の山が埋もれている可能性はある。それを掘り出す力が自分にあるかを考えて付き合う。他の人が掘り出したら、二番手で行くもの手だ。
・奥さんには言葉に尽くせない豊かな情報が潜んでいる。奥さんと話をするのは相手を知るのに有効な方法。
・誰かに何かをしてあげたいと思ったことのない男は危険、情が薄い。
・友達は若いときから自分が能動的に情を発し続けた延長線上に生まれる。
私は第一印象にそれほど信頼を置かないが、こういうことは言えると思う。「この人から何かをもらえる」という第一印象はよくよく考えた方がいい。しかし、
「この人には何かをしてあげたい」という第一印象は大事にした方がいい。
・「この人から何かをもらえる」という第一印象は信用できないが、「この人には何かをしてあげたい」という第一印象は大事にする。
・人間は無意識のうちに何かを望んでいる。人間を見るということは望むものを察することである。
・腐りかけはおいしいらしい。果物も女も、生ビールも。
・癖は変えられない。女房の癖を変えようなどと大それたことを考えてはならない。自然現象だと思え。
・人は誰でも自分の情念を透かして物事を見ている。
・スタンドプレー、自己アピールがオーバー、などと思う相手は、自分が好感を持っていない。
・敵が多いことは必ずしもマイナスではないが、敵が少ないことは明らかにプラスである。
・世間は人をよく見ている。世間の目、世間の評価は尊重すること。
・人間は他人を自分に引きつけて考えがちである。
・自分をひけらかすために無駄なことをやらせる人がいる。これが上司だと厄介極まりない。
・人生の落とし穴の避けるには、身を慎み、欲を抑えるしかない。ということは、実際問題として難しい。
・人間はうぬぼれの塊。自分と同じくらいと思う人はずっと上、しょうもないヤツと思う人が同レベル。つまり、自分を客観的に見れば、
しょうもないヤツということ。そう思うと、少しは謙虚になれるだろうか。
夫婦にしても、六〇歳になってまだ女房が夫に興味があるなんていうアホなことはない。しかし、結婚という枠にはめられているから、みな一緒に居る。
一般人の場合はその枠がない。そうなったら、もう、儂が俺が、である。
・こちらが話している時、相手が黙っているのは聞いているのではなく、話が終わるのを待っているのである。
・年寄りの話を聞いてやることで仲良くなれる。
・相手が誇らしいと思っていることを覚えておいて、時には口に出すことがいい関係を作る。
・たいがいの人の話は、どこかに勉強になるものが含まれている。ただし、どうしようもない人は一人か二人はいる。
・みんなが悪口を言っている時は、一緒に悪口を言わないと仲間はずれにされる。
他人への期待の上に何かを築き上げることはやめた方がいい。少なくとも、「あの人がこうしてくれることによって自分はこうなる」というふうに、
将来計画の中へ加算することは間違いではないかと思う。
普通、期待という言葉で世間は言うが、実質は要求であることが多い。つまり「何々して欲しい」ということだ。そういう「欲しがり屋」は
要求ばかりの旧社会党と何ら違いはない。
・説得するには数字が有効。納得させるには相手が受け入れやすい言葉が必要。
・仕事は世間にわかるようにやるべきだ。
・期待するなら自分からアプローチして人間関係を作る。待っているだけでは何も生まれない。
・特別な情報源はいらない。問題意識があれば、公開情報の中から役立つ情報が手に入る。
・読書と実生活を往復してこそ、読書が役に立つ。
私はこの年まで「こうしよう」「ああしよう」と思ったことはほとんどない。ましてや自分で人生の設計図を描いたことはいっぺんもない。そのときの流れにそって生きてきた。
人生とはそんなものではないかと思う。いくら精巧な設計図を描いたところで、それだけのことだ。設計図に偶然という要素を入れることはできないのだから。
株の名人野村徳七があと十年、株の投機に手を染めていたら大損した可能性だってある。いつも勝つとは限らないと思っていたから、大儲けしたらさっさとやめた。
これは見込みに引きずられない賢い態度である。
うまくいかないことが起こったら、「今はまだ完成に向かう途中だ」と思ったらいい。あるいは、人生という探検の旅で、氾濫する川に遭遇したと思えばいい。
困難のない真っ直ぐな道を歩くのでは探検にならない。山があり、谷があり、時には川が氾濫しているところを乗り越えていくから探検なのだ。
人生もそう考えれば、面白くなるではないか。
・質実剛健、木訥の裏面は恩知らず。
・人の面倒を見て、見返りを期待しないのが鉄則。
・人間関係は壊れ物。水を入れたコップをそろりそろりと持ち運ぶようなもの。
・人は寂しい生き物。誰かを頼りにしたい。
・人生は、いつの時点でも完成に向かう途中である。