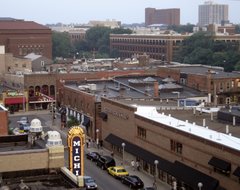『脳を鍛えれば今までの10倍うまくいく/ビル・ルーカス』
脳を正しく扱うための10のアドバイス
1.十分に水分を補給しておくこと。
あなたの脳は、「電気回路」を効果的に機能させるために多量の水を必要としている。
2.定期的に休憩して、身体を伸ばすこと。
脳が十分に機能するためには、酸素を含んだ大量の血液が必要である。立ち上がるだけで、血液の流れが20%も増大する。
3.いつも最初に全体像を示すこと。
あなたの脳は絶えずつながりを作ろうとしている。したがって、最初に全体像を示しておくことにより、細部に注意を向けることを好む人にも、物事の意味を理解したり、特定のテーマに関して自分が知っていることをすべて集めたりするための時間が与えられる。
4.人々に向かって長時間一方的に話し続けないようにすること。
あなたの脳は、一度に一定量の新しい情報しか取り入れることができない。話し手の力量が大変優れているのでない限り、聞き手の脳は20分ほどで停止してしまう。
5.情報を伝える方法に変化を持たせること。
私たちの頭は一人ひとり異なっている。視覚的な情報を好む人もいれば、聴覚的な情報を好む人もいる。また、立ち上がって何かをすることによって情報を取り入れることを好む運動型の人もいる。
6.集中力の持続する時 間についても考慮すること。
流れに乗っているときは仕事を続けると効果的であるが、20~30分ごとに定期的な小休止を入れると頭は仕事を継続しやすくなる。
7.大きな課題はいくつかの小さな部分に分けて、取り組みやすくすること。
いくつかの小さな要素に分解することによって、頭は大きな問題に取り組みやすくなる。
8.ユーモアを用いること。
笑うと、緊張をほぐす働きを持つエンドルフィンと呼ばれる化学物質が分泌されることがわかっている。
9.よりよい成果を出させたければ、恐怖心を与えないこと。
わたしたちの脳は、ストレス下では、生き残ることしか考えることができず、より高度な思考作用が効果的に行なわれることはなくなる。
10.必ず十分な睡眠をとるようにすること。
必要な睡眠時間は人によって異なるが、多くの人にとって、夜の睡眠は7時間以上なければ十分とはいえない。脳が疲労しているとき、脳はうまく働かない。
今から24時間前までを振り返ってみましょう。あなたは、脳の世話をどの程度心がけてきましたか?
あなたは10の簡単なヒントの中で、十分に生かしているものはいくつありますか?
あなたの生活には、どこかアニーの日常と共通している部分がありますか?
意識していないしできない
↓
意識しているができない
↓
意識していてできる
↓
意識しないでもできる
他者を模倣することによって確実に恩恵を受けるための10の方法
1.組織の中であなたが最も尊敬する人々と共に時間を過ごすこと。
わたしたちは、非常に短時間のうちに、身近にいる人々の持つ行動様式や物事への取り組み方から影響を受ける。したがって、分別のある時間の過ごし方をすることはとても大事である。
2.あなたが選んだ仕事の現場の中で、最も尊敬できる人を見つけて、彼らが実際に仕事をする様子を観察できる方法を考えること。
もし、自分の関わっている分野における最高の人々を見習うことができれば、あなたの成功の確率は高くなる。
3.自分の仕事ぶりを改善したいと思う領域を選んで、組織の中でそれを一番よくこなす人物を見つけること。
この種の具体的な模倣は、スキルを改善するための非常に積極的な方法となり得る。
例:会議の司会。フィードバックの方法。
4.模倣するための良い手本と提供するテレビ番組や映画を探す。
あなたの脳には、真似をする特性が備わっているので、脳に吸収させる情報には注意を払わばければならない。
5.尊敬する人々の伝記を読む。
伝記には、わたしたちの見習うべき、成功を招く行動についての洞察が含まれている場合が多い。
6.意識的に、職場であなたが見習いたいと思う人々と昼食を共にする。
わたしたちは昼食の時間を無駄に過ごしてしまう場合が多い。あなたが尊敬する人々と交友関係を持つことができれば、彼らの成功の方程式を発見するチャンスは高まる。
7.様々な分野において、あなたが手本にしたいと思うような行動をとっている人々を見つけて、彼らと交友関係を結ぶこと。
自分とは異なる仮説を持っている人々と一緒にいるときに、有用な洞察が得られることが多い。
8.職場にいる否定的な傾向を持つ人々と、不要な時間を共に過ごすことのないように留意すること。
あなたは何らかの形で、彼らの持つ否定的な傾向の影響を受けてしまうことになる。
9.困難な状況が見事に処理されるのを見たら、そのやり方を書き留めておくこと。
物事がうまく行ったと感じる自分の感受性を大事にすること。
10.あなたが手本にできる人々のネットワークを広げるための、交友と学習の機会を探すこと。
これはあなたが、「あらゆる種類の鳥たちの群れに加わる(フロッキング)」ことができるようにする方法である。
学習が困難になったときに取るべき10の行動
1.今やっていることをやめて、完全な休憩を取る。
2.以前同じように行き詰まったときのことを振り返って、自分が何をしたかを考える。
3.自分にとっての選択肢の概要を示すマップやリストを作る。
4.友人にそのことを話して、彼らだったらどうするかを尋ねる。
5.本を使って、突破口を見つけるのに役立てる。
6.インターネットを使って、答えを発見するために役立てる。
7.何か運動をして、答えが浮かばないか試してみる。
8.行き詰まりを放置して眠る。寝る前に「自分は問題の突破口を見つける」と自分に言い聞かせる。
9.自分が今やっていることを、まったく別の場所でやってみる。
10.もし答えが見つかれば、あなたの仕事の達成に役立つかもしれないと思える質問をできるだけ多く考え出す。
事態が混迷を極めるときに取るべき10の行動
1.心を乱さない。
2.自分に正直になって、自分の最初の目的を思い出す。
3.その状況に取り組む別々の方法を3つ考えて、その中に使えるものがないか調べる。
4.その状況で、実務家や理論家(自分と異なったタイプの人)であればどうするかを想像してみる。
5.別な人が同じ問題に対してどのような取り組みを行うかを、近くに行って観察し、彼らから学ぶ
(他者が見習うことは、不正行為ではなく、知性の発露であるということを思い出そう)。
6.電話をかけたり、Eメールを送ったり、本を参照したりして、その分野の専門家は、この場合に何をするか調べる。
7.あなたがしていることの詳細は知らなくても、常識にもとづいたアドバイスをくれそうな人や、あなたの考え方を変えてくれそうな人に尋ねる。
8.インターネットでヒントを探す。
9.その日のうちに、時間を変えてもう一度その問題に戻ってみる。
10.自分の学習を続けることが正しいことかどうかを、よく考える。場合によっては、それまでに自分が学んだことを振り返った上で、別なことをする方が賢いことがある。
発明とはアイデア同士の創造的な組み合わせ
本当に新しいアイデアというものは非常に少ない。ほとんどの場合、それはすでに存在しているアイデア同士の創造的組み合わせである。
●車というアイデア+鋼鉄の発明+蒸気機関の発明=鉄道
●手紙+ワープロ+モデム=Eメール
●ラジオ+カセットプレーヤー+ヘッドフォン=ソニーのウォークマン
●巨大な書店というアイデア+インターネット=アマゾン・ドット・コム
●何でも最後の最後にならないとやらないという、わたしたちの持つ傾向+ワン・ストップ・ショッピングというアイデア+インターネット=lastminute.com
●大学というアイデア+新しいテクノロジ-=バーチャル・ユニバーシティや企業大学
●「洗濯仕上げ用圧搾ローラー」と「洗濯板」を使った、昔の洗濯の仕方+逆方向に回る2つの桶を備えた最新テクノロジー=ダイソンの最新型洗濯機
MIT(マサチューセッツ工科大学)のニコラス・ネグロポンテは次のように言う。
新しいアイデアは相違から生まれる。それらは、見解の相違や、比較対照される理論の相違から生まれる。
アメリカの詩人ロバート・フロストは、さらに簡潔に、「アイデアは、連想の妙である」と言った。
幸運なことに、より深刻な症状が起きる前に発見することができる、多くの兆候がある。
次に挙げるのは、その一部分に過ぎない。
●怒りっぽくなる
●攻撃性
●過剰防衛
●優柔不断
●集中力の低下
●自信喪失
●持続的な疲労感
●筋肉の緊張。特に首・肩・背中
●頭痛
●消化不良
●不眠症
●便秘
●大量の発汗