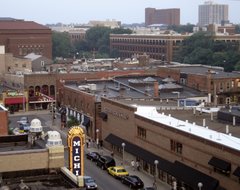「人間嫌い」のルール・中島義道
これほどの労力を払って人生を降りようとするのは、人間のある面がひどく「嫌い」だからである。人間が不純だからでない、不道徳だからでない、利己主義だか らでない、むしろ「よいこと」を絶対の自信をもって、温かい眼差しをもって、私に強要するからなのだ。とりわけ共感を、つまり他人が喜んでいるときに喜ぶ ように、他人が悲しんでいるとき悲しむように、私にたえず強要している。これを拒否して生きることはできない。だから、私は自分を徹底的にごまかして生き 延びてきたのである。そういう風に私を作った他人の鈍感さと傲慢さが嫌いであり、それにうまく合わせてきた自分のずるさと弱さがきらいなのである。
日 本社会をすっぽり覆っている「みんな一緒主義」、言葉だけの「思いやり主義」「ジコチュー嫌悪主義」が、少なからぬ若者を苦しめ、「もう生きていけない」 と思わせ、絶望の淵に追いやっている。善人どもは「いじめ」が問題になると、「あなたはひとりではない!」というメッセージを送ってのうのうとしている。 だが、自殺にまで追い込まれた少なかぬ者は、「みんな一緒主義」の砦を打ち砕き、みんなから排斥されてもひとりで生きていける、というメッセージが欲しい のだ。
「ずるい人」
平 気で嘘をつき、自分を実際よりよく見せようとあらゆる工作をし、相手に対してくるくる態度を変え、権威者や権力者にはおもねり、非権威者や非権力者を足蹴 にする人である。表面では正義感ぶって、裏に回るといかなる卑劣なこともしでかす人、こういう人が、これまでの人類の歴史で肯定的に評価されたことはな かった。
ひ きこもりやニートのほとんどは、先の定義において人間嫌いであるわけでない。人間嫌いという領域に属する者もいるであろうが、彼らの多くは、心の病とは無 縁である、―原因はさまざまであれ―単に社会性の欠如した者、他人とのコミュニケーション能力の欠しい者にすぎない。いまの苦境を抜け出してどうにか社会 復帰したい者、だがその端緒がつかめない者、あわよくば棚からぼた餅が落ちてくることを願っている者、ニーチェの言葉を借りれば「蓄群的功利性の持ち主に すぎない。
親切を押し売りする人は、他人がそれを拒否することなど考えもしない。いや、こんなに親切にしているのに、それを不快に思うとは何と無礼なと憤り、もっとたちの悪いことに「心の貧しさを悲しみ」、そこでぴたりと思考を停止してしまう。
困っ ている人、苦しんでいる人を見かけたら、淡々とした気持ちで助け、さらりとその場から立ち去る。そして、自分が何をしたか「忘れてしまう」のである。こう した助ける者と助けられる者との関係が、最も気持ちのいい人間関係を取り結ぶと私は信じる。できれば、助けるときも、助けられるときも、こういう淡白な関 係でいたい。
昔 の仲間たちとそれを懐かしむことが好きではない。中高年の鈍重さと醜さを曝け出して、「こんなことがあったなあ、あんなことがあったなあ」と笑い転げるこ とが嫌いなのである。その和気あいあいとした雰囲気は共感ゲームで充たされ、大量の欺瞞が飛び交い、みなどこまでもよい気分でいたいという欲望がグロテス クなほど露出されていて、気持ちが悪いのだ。
オルテガ
大衆とは、善い意味でも悪い意味でも、自分自身に特殊な価値を認めようとはせず、自分は「すべての人」と同じあると感じ、そのことに苦痛を覚えるどころか、ほかの人々と同一であることに喜びを見出しているすべての人のことである。
こ うした大衆は、知的に徹底的に怠惰であるから、何事においても、「わかりやすいこと」を求める。「わかりやすい」とは、何の努力もしないでわかるというこ と、書物なら寝っ転がって読んでもわかるということである。彼らにとっては、わかりにくい書物は全面的に著者が悪いのだ。
人間嫌いは、あらゆる人間からの独立を目指すと同時に、あらゆる土地、風土、故郷からの独立を目指す。
世の中は、二十歳の男には寛大であっても四十歳の男には寛大でないということを知っておけば、それでいいのだ。
私 は、常に崖っぷちを歩いてきたからこそ、そして思いがけず多くの人に助けられて生きてきたからこそ、どんなに型破りの生き方があってもいいじゃないかと心 から思う。一見、不安定に見える職業に就いていても、将来の見通しが立たないように見える状況に投げ込まれていても、その人固有の人生の「かたち」を描き きることはできると思っている。
この世のほとんどの不幸は、他人に過剰に期待することに起因するのではないかと思う。他人に期待することがなければ、他人を恨むこともない。他人の賞賛を求めることもない。
大 原則として、他人の人生に過度の期待をかけてはならないと思う。勝手に相手に期待して、その期待がかなわないとき、「こんなはずではなかった」と相手を責 めるのが卑劣な弱者というものである。人間嫌いが人間嫌いらしく生きるには、こういう人間関係からみずからを解放しなければならない。他人に夢を託しても ならず、他人から夢を託されてもならない。この関係の重荷からだけでもすっかり解放されたら、人生はどんなに楽になることであろう。
子供は親に、妻は夫に「ああしてくれ、こうしてくれ」と過剰に期待するから、それがかなえられないと激しく憎むようになる。同じく、親は子供に、夫は妻に、よい子であるように、よい妻であるように過剰に期待をかけるから、失望するのである。
人間嫌いにとっての理想的人間関係とは、相手を支配することなく、相手から支配されることのない、相手に信頼や愛をおしつけることも、相手から信頼や愛をおしつけられることもない関係である。
そ のころから、自分のえげつないほどの実利的で世俗的な能力、すなわちさまざまな形で人々を組織する能力、権力者に近づく(遠ざからない)能力、自分のアカ デミニズムとジャーナリズムにおける「地位」を担保にして、人を支配する能力、あるいは人に好まれる能力・・・つまり自分の生き方の「賢さ」に嫌悪感を覚 えるようになってきたのだ。
人間嫌いをその中核で動かしている動力は自己愛である。なるべく自分の感受性と信念とに忠実に、すなわち普通の言葉を使えば、なるべくわがままに生きたい。他の人のわがままも許すから、こちらのわがままも許してもらいたい。
―これが一番受け容れられないことだが、―人間の平等を認めないで、善良な市民の趣味に対してはひどく不寛容である。とくに、言葉遣い、身のこなし、着ている物に関して、私を侵害しなければ最低限いいとしても、(私の基準で)趣味の悪い人と一緒にいることは不快である。
家族主義的人間嫌いは、いまなおわが国の妻帯者の中に少なからず残存しているようである。彼は実存の深いところで妻に依存しているので、妻から切り離されて世間の寒空にひとりおっぽり出されたら生きていけない。
外部との間に厚い壁をめぐらせ、我が家のいかなるマイナス面も絶対に外部に漏らしてはならない、という子供たちに厳しく命じた。
こうした虚栄心だらけの家庭が厭でたまらなかったにもかかわらず、結婚して私は同じような家庭を築いた。
人間嫌いのルール
-
なるべくひとりでいる訓練をする
-
したくないことはなるべくしない。
-
したいことは徹底的にする。
-
自分の信念にどこまでも忠実に生きる。
-
自分の感受性を大切にする。
-
心にもないことは語らない。
-
いかに人が困窮していても(頼まれなければ)何もしない。
-
非人間嫌い(一般人)との「接触事故」を起こさない。
-
自分を「正しい」と思ってはならない。
-
いつでも死ぬ準備をしている。
人間嫌いの分類学
-
動物愛好型
弱い人間嫌い。人間は嘘を付くから嫌い。その点、動物は正直でいい、という思想を基本的によりどころにしている人。動物園勤務の人に多い。幼稚園、保育 園や小学校も。あるいは、童話作家。これは、「人間嫌い」というよりも「大人嫌い」。良寛、宮沢賢治、灰谷健次郎など。
-
アルセスト型
モリエールの古典『人間嫌い』の主人公アルセストのようなタイプ。人間の心の醜さやずるさに辟易して「人間はなぜもっと美しい心をもてないのだろう!」 と嘆くタイプ。自分は純粋だと思っている分だけ、自己批判精神が欠如している。精神的発育不良。太宰治などはこのタイプ。自殺する者も少なくない。
-
自己優位型
アルセスト型は未熟な人間観に基づいているのに対して、このタイプはもう少し実質が伴っている。だからこそ、最もたちが悪いとも言える。人間嫌いのうち では、これが一番多いタイプ。世の中にいるバカな人や鈍感な人や趣味の悪い人などと、どうしてもうまくやっていけない。それは自分が優れているためであ り、彼らが自分の高みに至らないためである。だから、このすべては自分の責任ではない。自分は微塵も変えずにいていいのだ。自分には、愚鈍な輩を嫌う「権 利」があるのだ。典型的には三島由紀夫や芥川龍之介。少し自己反省を加えると夏目漱石。ほとんどの芸術家も、実はこう考えているようだ。
-
モラリスト型
人間の心の醜さに嘆き顔を背けるのではなく、それをあえて観察の対象にしようと決意した人間嫌い。人間の細部に至って観察し続け、その滑稽さ、卑小さを 炙り出し、「おもしろい」と呟き、どうにか人間に対する絶望から逃れるタイプ。パスカル、モンテーニュ。カントにニーチェ。
-
ペシミスト型
人間や人生に対して深い恨みを持っているタイプ。所詮この世は生きるに値せず、人間は醜い、この世は闇だと言い続けることによって、かろうじて均衡を保っている。永井荷風。
-
逃走型
芭蕉や山頭火のように、社会から逃れて放浪するタイプ。あるいは、西行や鴨長明のように、山に篭もるタイプ。サン・テグジュベリのように大空に「ひきこもる」者もいる。彼らは、一般的には人間を愛しているのだが、個々の人間は大嫌いだというコントラストのうちにある。
-
仙人型
きわめて少ないが、世の中を達観した人間嫌いであり、おろかな俗物どもを「優しく見守る」人間嫌いだ。悟りに至った禅僧などはこの部類に入る。